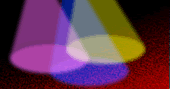
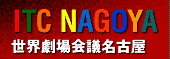
《文化振興基本法セミナー》
■中川幾郎氏講演「文化芸術振興基本法をめぐって」
※以下は2002年5月11日金谷ホテルで行われた公演内容の要約です。
◇文化芸術振興基本法の成立までの経緯
法案提出までは、公明党の取り組みが先行、音楽振興議員連盟が推進し、超党派で行われた。
⇒政党主導による文化政策のてこ入れ 超党派の取り組み
昨年6月、公明党より、中川氏の所へ、関連する資料が届いたことがあった。
昨年9月下旬に、突然、法案が提出され、可決の方向であることが判明する。
⇒議員立法としての法
どちらかといえば、多くの人たちが待ち望んだ法律であり、肯定的に考えたが、なおいくつかの問題点が見受けられるため、 国民的な広範な議論とそのための時間が必要である、と数十人の研究者たちがより広範な議論を提案した。
その結果、これまでに、芸団協参加の人たちからをはじめとして、上記の研究者たちとの間でいくつかの議論が起こってきた。
舞台芸術団体(芸団協等)は、これまで、高コストの舞台芸術に対する公的支援制度の拡充と これらの法律の成立を長年望んできており、息の長い運動をしてきた。
舞台芸術団体から研究者への批判
批判1)この法律が成立しなければ、誰が責任をとるのか。(このチャンスを逃して、成立などありえない。)
批判2)研究者、学者は感度が鈍い。今頃になってクレームをつけるとは、これまで何をしてきたのか。 (我々の切実な努力をどう考えるのか。)
批判3)研究者が危惧するような国家的文化統制、弾圧など、今日の時代では考えられないのではないか。
反論
反論1)文化的人権の視点が不明確な、国家的容喙に道を開くような不完全な法ができたら、誰が責任をとるのか。
反論2)法律系の特定研究者を除いて、国会で審議されている法案をたえず注視している研究者ばかりではありえない。 また、問題提起をしている研究者の幾人かは、むしろ政党等の助言を求められて、真摯に対応してきた者たちであり、 それがために、法案提出以前の政党側の情報公開と国民的議論の広がりを望んだのである。 むしろ議員立法であるがゆえに、複数政党による積極的な情報公開と国民的討論が必要であったのではないか。
反論3)重要なのは、公的支援の必要性と同時存在する、支援される芸術の表現内容等への不介入の原則の明記である。 権力批判、政府批判の内容を有する芸術への、恣意的無関心・放置によって、芸術を国家的に差別化し序列化することは 十分可能である。これは、英国サッチャー政権時代に現実に起こったことでもある。
舞台芸術団体の一歩前進論、無いよりあったほうが良い論に対して、後進的な内容の法律の定着に異議を唱えた。 集権的な、文化庁直轄型の国の補助金分配への期待論を感ずる。地方自治体が中心の文化行政体制がこれからも重要である。
◇文化芸術振興基本法のあらまし
理念
『基本理念
第二条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。
2 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行うものの創造性が十分に尊重されるとともに、 その地位の向上がはかられ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
3 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ、 国民がその居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、 又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。』
国会答弁においては、この部分が、芸術への不介入の原則を説明していると述べられているが、われわれの認識では、 これは、自然権的記述であって、尊重しようという認識論で止まってしまう。 干渉介入があって、訴訟を起こした場合、この条文では、訴えを正当化できない。
さらに国民の文化権、つまり世界人権宣言を受けた国際人権規約に明記されている、「文化的な生活に参加する権利」は、 この条文では担保できない。
施策の例示方法
第三章の第八条から第三十一条までがその内容であるが、第八条から第二十一条までは、 現在の文化庁の実態的な事務分掌内容をほぼ踏襲して掲載したものである。 文化庁が現在行っている、宗教法人の認可を除く、国語政策、国際文化交流政策、伝統芸能政策等を、 そのまま追随して掲載したに過ぎないのではないか、文化省設置法のようだ、との意見も出ている。
評価できる点は、第二十二条の「高齢者、障害者の文化芸術活動の充実」が特に 明記されたことだが、「文化権」の明確な記述があれば、これも当然に包含される政策となる。
法律における施策の例示方法には、制限列挙(限定列挙)方式と事例列挙方式があるが、この法律は、 付帯決議で確認されたとおり、事例列挙方式である。この点を、今後も十分に認識する必要がある。 事業例示に誘導されないことが重要。
国と地方自治体との関係
地方自治体との関係については、<第四条 地方公共団体の責務 地方公共団体は、 基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、 その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。>及び <第三十五条 地方公共団体の施策 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、 その地域の特性に応じた文化芸術の振興のために必要な施策の推進を図るよう努めるものとする。>で、触れられている。
一昨年改定施行された地方自治法では、国と地方自治体は対等の関係とされたはず。 こういった国と地方自治体の関係については、当然、地方自治体の意見を取り入れる必要があったはずである。
第三十五条の「勘案」の受け止め方によっては、第八条から第三十四条までに書かれていることが、 実施すべき文化施策の全てであると、鵜呑みにしてしまう地方自治体が出てきかねない危惧を感じる。
第四条については、国と連携を図りながら、自主的かつ主体的と、矛盾した関係が記述されている。 地方自治体の主体性を損なうことは、改正地方自治法第1条第2項第2号の解釈からも許されないと思う。 したがって、この「連携」の意味を具体化するには、対等な関係におけるむしろ国側の役割分担を明記しなければ明確にならない。
国と民間活動との関わりは4例ある。1)規制 2)助成 3)補完 4)直営 である。 このことは、芸術文化に関しては、国と地方自治体の関係でも当てはまると思う。地方自治体の財政能力では展開することができない案件や、全国的な展開の必要性がある案件についてのみ、国が補完的に参画すべきであって、地方自治体が、国の政策に従属的に「連携」する必要は全く無いと考えるべきであろう。
また、第三十五条の<国の施策を勘案し>に沿って、これだけオールラウンドな政策に対応しようとすると、地方自治体の弱小な芸術文化予算では、薄く浅くなってしまう。さらに、地方自治体の政策的な主体性は発揮できなくなる。大都市は別として、人口が十万人以下の市町村では、これだけのことを行おうとすると、何の政策効果もない、ばらまきの文化政策になってしまう。それでは自治体の政策選択性及び政策主体性を損なうおそれがある。この「勘案」の内容も、「連携」の内容と表裏一体である。
◇指摘されている問題点
文化権について
文化権の定義、明記を強く望んだが、あいまいな規定で終わってしまったことは残念である。最近制定された、北海道士別市の文化条例には、文化権の規定も書かれているし、行政不介入(アームス・レングスの原則)も明記されている。
アームス・レングスの原則
イギリスの芸術評議会について、ケインズによるBBC放送での有名な宣言<金は出すが、口は出さない>がある。イギリスの芸術評議会は、国の支援を受けた第三者機関であるので、この原則は可能であるが、政府内機関では不可能である。現在、論議されている、マスメディア規制法や人権擁護法についても、救済機関が法務省内部の政府内機関であるから、政府の行う人権侵害に対して救済可能か疑問視されている。この、文化芸術振興基本法の政策形成機関は文化芸術審議会であるが、これは、文化庁の内部機関である。
アームス・レングスの原則とそれを保障するシステムを条文に明記すべきであったと思う。
政策決定システムについて
文化芸術審議会は政策形成機関である。政策決定機関、政策執行システムが明らかにされていない、イギリスの芸術評議会にならって、芸術家、芸術団体、政府代表、国民代表等、需要者、供給者、公的支援者で構成される第三者機関を設置し、政策を決定することが重要である。
しかしながら現在、イギリスのアーツ・カウンシルについては、批判がないわけではない。長期に亘って理事メンバーが固定(しかも後任は前任の推薦方式)されていることやプロパーの官僚化に問題がある。要職の独占の禁止、及び作品選定、助成支援の決定等について客観的かつ明確な指針を設け、かつ、審議、決定経過の公開が必要である。わが国や地方自治体においても、支援、助成等の作品選定、個人、団体選定について、これまでの、「有識者」によるあいまいな選定ではなく、評価軸を設定し、情報公開するべき時期に来ている。
用語及び定義について
これまで用いられている、<芸術文化>ではなく、なぜ、<文化芸術>なのか。国会答弁では、「芸術にとどまらなく、広く国民文化全般に渡っている。」とされている。文化とは、あくまでも価値の体系であるので、その中の何を対象にするかという意味で、<芸術文化振興法>とすべきであった。そして、<文化基本法>と、分けて作るべきであったと思う。文化に関する国民の権利と、政府の行動原則を定めるものは、後者である。芸術文化振興の施策、政策の方向性を定めるものは、前者である。本来、別の二つのものを一つに盛り込んだ点に、問題点がある。
第六条、第七条のみ<政府>という用語が使われ、その他は全て<国>である。同義で使われているが、各政党案をばたばたの状態でまとめたために起こったものでものであろう。特段の支障は生じないとは思われる。
<芸術><芸能><伝統芸能>が混在しているが、本来、<アート>の語義に基づいて定義し直すべきであった。このままでは、あいまいな定義を定着させ、ある種の差別性を固定化する危険性がある。
さらに、第十二条に<生活文化(茶道、華道、書道その他の生活に係わる文化をいう。)>という用語が出てくるが、このようなものを<生活文化>と呼ぶのは一般的ではない。習い事やアマチュア活動でも、芸術に違いはない(生活芸術という言い方もあるが)。ここには、誤ったプロ、アマ論が存在していると思える。衣食住に係わる<生活文化>と非日常的な<芸術文化>がそれぞれ照応し、互いを支え合い、高めあうのが本来の姿である。これまでのさまざまな芸術研究、文化政策研究で確立している論議に立っていない。
集権か分権か
この法律によって、政策的自立を考えていない居眠り型の自治体は、この法律のままやればよい、で済ませてしまう恐れがある。また、梅棹忠夫先生が20年前に唱えられた「チャージ・ディスチャージ論」によって、これまで、首長部局へシフトしてきた地方自治体の総合的文化政策が、この法律が文化庁の所管であることで、教育委員会所管の狭い文化行政へ逆戻りする危険性もある。
また、このあとに、「劇場法」を作るべきとの議論がある。公立ホールは、地方自治法に規定されている「公の施設」に係わるので、これについては、総務省との議論が必要であり、公立ホールのためだけに地方自治法の改正は難しいとの声がある。今後の議論を待ちたい。
図書館、博物館、公民館等は、社会教育の施設で、社会教育法第二十三条が適応される。それは、「営利、宗教、政治活動に使用してはならない。」というものである。
ただし、文化ホール、公立ホールは社会教育法上の施設ではない。にもかかわらず、公立ホールの建設には、これまで、文部科学省、文化庁の補助金が交付されてきている。そのために、二十数年前に、「社会教育法上の施設ではないけれども、教育委員会の管轄も是とする。」との趣旨の通達が出されている。このために、各地で教育委員会所管の公立ホールがいっぱいできた。これに対して、前述の梅棹先生のマニフェスト(宣言)と論文が出され、次第に首長部局型の総合的文化政策へ移ってきたものを、文化庁・自治体教育委員会所管型の画一的文化行政に逆戻りさせることになりかねないことを危惧する。
<第三十二条 2 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医療機関等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。>の項は、今まで以上の大きなエリアにウイングを延ばして、文化政策をとらえることにはなる。だが、自治体の文化行政・文化施策の総合性確保は、文化庁・自治体教育委員会所管では難しい。
◇予想される効果(波及性)
民間
沖縄県の琉球大学教授中村透先生が関係しておられる、シュガー・ホールでの出来事だが、 ホール職員の長期定着を図ったら、職員たちが文化庁等の助成、補助の内容に精通するようになった。 やがて、助成、補助の対象になりやすい事業ばかり企画するようになり、 町や地域のオリジナルや住民のニーズに着目しないようになってしまったそうである。 これは、内発的な中央集権化、公的補助システムへの無意識の馴化である。 この法律には、この点での、事業誘導の効果も予想される。
この法律によって、コストがかかる舞台芸術関係に関しては、今より状況がよくなる可能性はある。 今回も、たしか500億円ほどの予算額増になっていると聞く。 ただ、これを文化庁独自で補助、助成処理できるとは思えないので、何らかの中間団体への推薦の要請が起こると思われる。 先般話題となったNGO組織のように、実態的にオーソリティーになってしまう団体に 分配機能が一部帰属してしまうおそれがある。 したがって、先ほども述べた、政策決定のシステムと事業選定のシステムを第三者機関で独立させ、 選考基準のシステムの確立、及び情報公開を行う必要がある。
絵画、美術館関係の団体のように、コストがかからない芸術、特に文学等は、この法律に全く無関心である。 イニシャルコストが必要な芸術文化団体の期待とその他の団体の落差が大きく存在する。 しかしながらこの法律の効果は今後、全てのジャンルに影響を及ぼしてくると予測される。
地方自治体
この法律に対する自治体の反応には、いくつかのパターンが予想される。一つは、この法律ができたから、自前の条例の必要はなく、このとおりにやればよい、という従来の機関委任事務型で、この法律に安堵している自治体。もう一つは、この法律に疑問と不信を感じている自治体、つまり、これまで、地域の独自色を発揮してきた自治体。三つ目は、これはこれでいいけども、住民や議会の要望があれば、条例を作らなければならないのかと、他市の動向を様子見の自治体。
関西の動向
大阪府内では、人口規模の大きい自治体ほど、この法律を唐突に感じているようである。大阪府自体は、今のところ反応があまり見えない。民間レベルでは、大阪文化団体連合会の文化条例検討委員会が、2年半ほど前から、文化条例素案を作成し、行政や周囲に公開・提示してきている。その中には、文化権が明示され、アームス・レングスの法則も謳われており、政策実行システム、事業選択システムも、大阪府民文化会議として提起してある。また、大阪府文化議員連盟も、先般発足した。早ければ1,2年後に、議員提案条例が、議会に上程されるのではないか、という予測がある。
神戸市では、平田 康先生らを中心メンバーとする「神戸をほんまの文化都市にする会」が、神戸市の文化基本条例の草案を作成し、神戸市との議論、市民運動化等が本格化してきている。これは、文化芸術振興法の成立で、逆に弾みがついたようである。
関西でも、全国の例にもれず、地方自治体の、文化担当の部長・課長が極めて短命であり、さまざまな引継ぎが十分になされない。この点は、地域の文化団体は、十分な引継ぎを行うか、懸案事項がある場合は移動させないよう要望すべきである。また、担当者の訓練と資質も重要である。単なる趣味人では、文化担当の責任者は勤まるはずがない。必要分野の研究、学習能力、マネージメント能力が重要である。また、文化政策についても、政策とはなにかを理解し、政策企画をシミュレーションするトレーニングが必要である。
地方自治体文化担当者の文化団体向けの挨拶で、文化については素人でとか、文化や芸術のことはよく分かりませんので、といった口癖をよく聞くが、たとえば障害者行政担当者が、障害者問題について私よくわかりませんがよろしく、などと言えるだろうか。文化担当にはなんとなく許されてしまっているこのような状況を、早急に危機感を持って改めなければならない。
文化については、都市政策の重要分野であること、市民の文化的人権、ひいては精神的・肉体的生死にすら関わるということを、ティーチインしなければならない。とはいえ、大きな自治体になればなるほど、文化担当課長が、文化団体対策課長となってしまっている例が多い。文化団体のさまざまな要求を処理する役割のみを担っているが,本来は、ともに、丁々発止と文化政策を議論しあう関係であらねばならない。
地方自治体にとって、この法律ができたから、文化条例が必要ないとはならない。それは、地方自治法があるから殆どの条例はいらない、まして自治基本条例などはいらない、とはいえない事と同じである。自治基本条例を定めて、住民自治のシステムを定めることは必要であるし、法律の範囲内で、それぞれの自治体の独自性を発揮する条例を定めることは重要である。条例によって、住民投票の制度を定めることも可能であるし、政策評価システムの指標を定めることもできる。憲法と各種法律の関係と同様に、法律と条例の関係は、より細目を定める意義と、その地域の独自性を作り出すものである。よって、各自治体に、文化振興条例が作られることは、大変重要である。まして、自治体文化政策は、自治体独自の政策領域であり、この法律に縛られるようなものではない。
これまでに、各地方自治体で作成された文化振興基本計画の洗い直しも必要である。その内容は、現在、景気の悪化の中で、かなりのものが「凍結」または「安楽死」の状態となっているが、文化権、人権法の視点から、その重要性を認識し、今一度見直す必要がある。綜合計画では、都市改造のための道路整備、施設建設計画等において、期限や詳細な数値が決められているが、人権や文化については、全て、抽象的記述のままとなっていないだろうか。
また、組織的にも、首長部局と教育委員会の連携が取れる組織になっているか、今後も、問い直さなければならない。
◇まとめ
この法律のようなものを、国レベルで制定している国は、ヨーロッパにおいては殆どない。特にドイツとかオーストリアでは、地方が主体性を持ち、州法で定められている。それが、市レベルへさらに委ねられている。フィンランドでは、国の責務として、州レベルで担いきれないもののみを国の文化法として制定している。ヨーロッパの中で唯一の例外はフランスである。 フランスは、国レベルの中央集権的な文化政策をとっている。
この法律の中で、「世界に誇る日本文化」と記述されているが、先験的な<日本文化>なるものは果たして実在するのであろうか。全て、地方で発生し育ってきたものが、結果的に日本を代表する文化となっているのである。その意味でも<日本文化>の活力あるインキュベート機能を持つ、地方のアイデンティティ、プロパティをより重視する法律であってほしかった。
文化についての尺度は、地方ごとに異なってよい。公共性について考えれば、<芸術は公共財である>といわれることがあるが、芸術については、準公共財もあれば私的財も存在する。支持されずに滅んでいく芸術もいくつかある。また、日本全国共通の公共性はごくわずかであって、芸術についてそれを決定するのは、現在生きるわれわれでしかない。それは、時代により変化し、地域によっても異なるものである。また、対象となるものによっても異なるし、支援する人々によっても変わってくる。
箕面市においては、かつて、忠魂碑を建てたことで住民の異議申し立てを受け、公費の違法支出として憲法違反の判決を受けている。しかし、近隣の岸和田市においては、神事であり祭礼である、「だんじり祭り」が公的支援を受けて行われている。このことに、岸和田市民は誰も異議は唱えない。これに明らかなように、地域によって公共性は変化するものであり、地方自治体の文化政策も個性的であるべきである。
それに対して、この法律に盛り込まれている、あれもこれも取り入れる姿勢、付帯決議のように相撲から武道まで包括していることは、ただでさえ乏しい地方自治体の財政では、均等ばらまきとなり、なんら有効性を発揮できない。わが町は村歌舞伎の保存顕彰に最大投資する、わが町は社会参加できない青少年の救済策のためにコミュニティアーツを重視する等、それぞれ異なるべきである。また、大都市とそれから離れた地方都市の文化政策は当然異なるべきである。大都市から遠く離れた地域では、大都市で行われているプログラムを住民が鑑賞に出かけることが難しいので、それを地域へ招聘して公演することは公共性としてなりたつが、大都市周辺の自治体では、公共性となりにくい。だから、一律に、文化は公共財であるとは言いにくい。
文化政策の効果については、その地域がいかによりよく変化したか(有益な社会的変化すなわち「効果性」)が重要であって、いかに安価ですんだか、多くの集客があったかという点は、効果性とは異なる経済性、効率性のみの評価である。大きなホールで有名歌手の歌謡ショーを行えば、集客力は上がり、単価は下がる。
しかし、それで、市民としての自治意識や自治能力が高まるような効果は上がるのであろうか。地方自治体は、数量主義や科学主義で文化政策の基準を作成するのではなく、その地域が抱えている問題や、守るべき価値の問題と関わって政策評価軸を構築すべきである。さらに価値観や価値軸をいかに多様化・拡大していくかが、文化政策の心臓部であると思う。学校教育の中でも、芸術教育が行われていないので、ますます先細りである。それを、行政の社会教育のなかでどう充填するかの戦略を持たなければならない。
以上、申し上げたととおり、それぞれの地方自治体が、主体性をもってさまざまな政策立案、対処、対策を行わなければ、この法律に依拠するばかりでは、金太郎飴の自治体文化政策が蔓延する状態を生み出す危険性が大いにある。