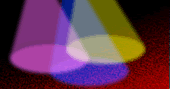
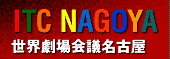
《世界劇場会議 国際フォーラム2010》
セッション・プログラム
| 2月12日(金) | |
| 13:00- | 開会式 |
| 13:30- | 基調講演 「がんばれ劇場!」
◆講師 ◇運営・企画について 佐藤 信 ◇建築について 伊東豊雄 |
| 15:30- | Session 1 座・高円寺 伊東豊雄・佐藤信が名古屋で語る 今、最先端の『がんばる劇場』座・高円寺(杉並区立杉並芸術会館)を語る。 新しい公共劇場をめざし「元気と文化が生まれる街」東京都杉並区高円寺に2009年5月1日にオープンした「座・高円寺(杉並区立杉並芸術会館)」が今、 注目を集めている。 伊東豊雄氏設計の劇場に佐藤信氏の芸術監督、指定管理者としてNPO法人劇場創造ネットワーク斉藤憐館長の組み合わせで、舞台芸術の創造と発信が始まった。 地域に根ざした文化活動の拠点として、様々な仕掛け『可変する小劇場・使いやすい区民ホール・阿波おどりホール・作品創造支援諸室・カフェ・ さざんかねっと・なみちけ・主催公演提携公演・劇場創造アカデミー・高円寺阿波おどり』を駆使し、 『がんばる劇場』座・高円寺から21世紀の地域公共ホールのあるべき姿を考える。 ◆講師 伊東豊雄(伊東豊雄建築設計事務所代表) 佐藤 信(座・高円寺芸術監督) ■コーディネーター 清水裕之(NPO法人世界劇場会議名古屋参与/名古屋大学大学院環境学研究科教授) |
| 19:00-21:00 | レセプション (会場:名古屋国際ホテル) |
| 2月13日(土) | |
| 10:00- | Session 2 劇場をめぐる環境 劇場をめぐる法的環境整備の可能性を探る。 経済状況の悪化が続き2001年をピークに我国の劇場鑑賞数は激減し、公共ホールの自主事業実施館数や事業費も減少の一途をたどっている。 このような社会情勢の中、本年4月に日本芸能実演家団体協議会は「社会の活力と創造的な発展をつくりだす劇場法(仮称)」を文化庁に提言した。 公共劇場への支援を契機に国民の芸術鑑賞の飛躍的な拡大をめざし 全国的な規模で研究・創造・鑑賞・参加の拠点としての専門家が配置された劇場・音楽堂等を創り上げる戦略的政策の構築を求めている。 2007年には劇場等演出空間運用基準協議会が設立され、全ての演出空間での自由な創造と作業の安全を確保する共通のルール作りが不可欠だという認識から、 本年4月に「劇場等演出空間の運用および安全に対するガイドライン」が発行された。 しかし、我国の現状は、演出空間という「場」の規定もなく、劇場という創造のための機関への支援もない。 このセッションでは、既に劇場に対する法整備を持つフランスやイタリアの劇場政策・法制から学び、 我国の「劇場法(仮称)」制定への現実的な課題と対応を討議する。 ◆講師 Xavier Greffe(パリ第一大学(パンテオン・ソルボンヌ)教授) 根木 昭(東京藝術大学教授) 大月 淳(名古屋大学大学院環境学研究科助教) 角 美弥子(政策研究大学院大学研究助手) 山出文男(愛知県舞台運営事業協同組合) ■コーディネーター 垣内恵美子(政策研究大学院大学教授) |
| Session 3 市民目線の劇場運営 市民(住民)目線の劇場はココだ! 劇場は、管理・制作・技術が三位一体化され市民目線で運営がなされているのが本来の姿ではないだろうか。 直営、指定管理、民間などさまざまな運営体系を持つ日本の劇場の中で利用者(使用者)あるいは観客としての市民は、劇場に一体何を求めているのであろうか。 また、運営者側は利用者あるいは観客としての市民に、どのようにアプローチしていけばよいのか。 市民の応援で劇場を管理運営している劇場にスポットを当て、劇場運営から地域発信まで、地域住民の心によりそった様々な工夫や発想を検証しながら、 劇場が地域に受け入れられ、地域文化の核となっていくためには何が必要なのかを、「市民の目」をキーワードに読み解いていく。 ◆講師 水戸雅彦(仙南芸術文化センター[宮城県]所長) 菱川浩二(多治見市文化会館[岐阜県]統括責任者) 漢 幸雄(あさひサンライズホール[北海道]主幹) ■コーディネーター 山田 純(名古屋芸術大学教授) |
|
| Session 4 学生アートマネジメントセッション 未来の芸術文化の発展を担う学生たちへ 今日、芸術文化をとりまく環境は、景気後退による財政難や指定管理者制度の導入など転換期を迎えている。 このような中で、地域との連携を基軸として、戦略的に振興していくことのできる人材育成はさらに必要度が増している。 芸術文化を支える人材に地域とのコミュニケーション力が求められる現在、大学時代の経験は、アートマネージャーとして活躍する将来、 貴重な財産となるであろう。 このセッションでは、大学でアートマネジメントを学ぶ学生自らが、「まち(劇場)と大学」がどのように連携しているか事例紹介を行うとともに、 大学における「アートマネジメント教育」を再検討し、全国規模での学生の意見交換の場とする。 ◆発表予定大学 東京藝術大学 静岡文化芸術大学 名古屋芸術大学 京都橘大学 他 ■進行役 小暮宣雄(京都橘大学教授) |
|
| 15:00- | Session 5 演劇にとって国際交流とは何か? 他者と出会う場としての劇場の可能性をめぐって 劇場という場、演劇という芸術形式は、21世紀において、異文化との交流・協働にどのようにかかわり、またどのようなことができるのだろうか。 海外から優れた舞台を輸入し、開催地域の住民が受動的に鑑賞するという一方的な「出会い」を喧伝する、 あるいはその演目を目当てにした国内外からの観客のもたらす経済効果を期待するような浅薄な国際芸術祭は未だに多くあるが、 それでは創造的出会いの場としての劇場の可能性は見えてこないだろう。 経済産業の分野でグローバル化が声高に叫ばれて久しい今日、地域を越え、文化を越えて創造的な出会いを演出するイベントとしての演劇、 あるいは他者との邂逅を創出する空間としての劇場はどうあるべきなのだろうか。 舞台芸術を通して、アジアの人々との新たな関係を築き、新しい作品を創り出す現場に関わる方々を招き、いま劇場にできることを考えてみよう。 ◆講師 畠 由紀(国際交流基金文化事業部舞台芸術チーム) 宮城 聰(静岡舞台芸術センター芸術総監督) 辺 発吉(中国呉橋国際雑技大会実行委員会事務局長/中国人民政治協商会議全国委員会員) ■コーディネーター 南 隆太(愛知教育大学教授) |
| 18:00- | 閉会式 |
■申し込み・問い合わせ
「世界劇場会議 国際フォーラム2010」実行委員会
〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-14-12 グランビル2B
特定非営利活動法人世界劇場会議名古屋内
TEL&FAX 052-232-2270
e-mail F10@itc-nagoya.com
◆案内チラシ